自作品たちの「創作日記」(その2)
自作品たちの「創作日記」(その1)
2023-01-18
きょうは1月18日水曜日。おととい・きのうと仕事が捗りはじめました。やはり、目だけでなく耳も、なにかに集中し、あるいは占領されれば、ほかのやるべ きことが疎かになりがちなことが、身をもってわかった今日このごろ。そう、いま最優先すべきは創作、英訳そして出版業務。β波大出力のあの放送局は、楽し いけれど、すくなくとも創作モードの時は向かない。いや、それどころか、先へと進めない。なので、のべつに聴くのではなく、上手につき合わないと、時間だ けが空回りで過ぎてゆくことになる。ラジオはやはり録音に任せて、あとで選択的にチェックするしかない。さて今朝は、例の場所に行くことにしょう。
Today is Wednesday, January 18. Yesterday, Shigoto[My own work] began to progress the day before yesterday and yesterday. These days, I've come to realize through experience that not only the eyes but also the ears tend to neglect other things when they are concentrated or occupied by something. Yes, the top priority now is creation, English translation and publishing. That broadcasting station with high β-wave output is fun, but at least not suitable when in creative mode. No, on the contrary, I can't move forward. So, I shouldn't listen to it all the time; if I don't get along well, time will pass by in vain. After all, there is no choice that the radio is left to the recording and checked selectively later. Well, I'm going to go to that place this morning.
↓
よかった! とてもよかった! 綺羅綺羅な海の細波を眺めたし、その写真も思う存分撮ったし、もちろん仕事も捗った。
ん?メッセージの下書きって仕事なんかい?
え?まあ…その…集中できた、という点では、じつによかった。しかも、車中仮眠と光る海の撮影も含めて3時間半も気持ちよく、静かな環境に浸ることができたし、しかもその間
(かん)、1円も使ってない! この総値上げの時代に、なんてすばらしいことだ!(^^;
2023-01-16
きょうは1月16日月曜日。早くも今月の中日ですね。時間は待ってくれない。急がなくては。でも、ころばないように^^;
Today is Monday, January 16. It's already the middle of this month. Time will not wait. I must hurry. But don't fall down ^^;
↓
それにしても、きょうはいつもの生活パターンを変えて、朝から出かけて、あの公園に行き、やはりピッカーン!なお天気じゃないとイマイチなことを確かめたあと、ぐるっと回って、午前中から行きつけのマクドでノマド。これがじつに捗りましたね。これまで、午前中は部屋のなかでまったりとラジオを聴きながら、仕事をしていたけれど、どうもいま一つ捗らなかった。
最近は、サイマルラジオの受信情態は、かつての音詰まり(配信遅延)がなくなって、極めて良好な状態にあるので、番組は録音に任せて、ノマドは朝10時前後からお昼ちょっと過ぎまですることにしようかな。平日の朝はお客も少なくて、思った以上に静か。ノー味噌もまだ疲れていいないので、新鮮みのない自分の部屋にいるよりずっと捗ることがわかった。
昼になると昼食のためのお客さんが増えてきてざわつきだすし、さらに園あとは、学校を早退した?学生さんたちがわらわらとやってくることが多く、そうなると私語が飛び交うので集中できなくなるため、早々に退散。きょうもそうでした。
で、そのあとは、お天気もよかったのでノマド先をハシゴするのは止めて、例の公園にもう一度立ち寄ってみました。すると、ここも静かで、なかなかいい。よく行っているリバーサイドパークもいいけれど、このシーサイドパークもなかなかいい。海面いっぱいにキラキラと煌めく波頭のたゆたいが美しい時間帯はすぎていたけれど、きれいに整備された公園の静穏な佇まいが心地いい。
そこで、愛車の後部シートに座って、マクドで捗った仕事の続きをやってみたら、ここでもいい感じでうちこめる。うーん、ここはいい! 無料だし、時間を気にせず、隣りの話し声を聞かされることもない。これから午後はここに日参しようかな。やはり、静かな環境でないと、本当の集中(集中力の持続)はできないことが、きょうの朝のノマドと午後の車内ワークで、あらためてよくわかったしだい。
じゃあ、日々のラジオ聴取はどうしよう? 正直言って、ラジオも聴きすぎると、自分のような、ルーティンワークではない、創作ベースの仕事になると、その進捗具合にブレーキがかかることが、今回のことでわかりました。
不在の間は録音を続けて、あとで、お気に入りの番組やコーナーをチェックすることにしようかな。そうでもしないと、やっていることがクリエイティブ・ワークなだけに、トークや音楽に気が散ってなかなかすすまないのでね。
2022-10-07
いまは未明。うん、なんかいい感じになってきた。きのうで峠は越えた。あとはなだらかな下り坂が降りてゆくだけ。ただ、所どころに険しい道があって、転ばないようにしないといけない。でも、道に迷うことはない。この道はまだかなりな距離はあるけれど、到着地点はすでに見えている。
そう、もうトンネルの道を歩いているわけではない。おとといまでのトンネルの道は、きのう突然峠の道に変わり、いまは到着地点に向けて、その途を降りはじめた情況だ。「草稿完成」というゴールまで粛々と歩いてゆこう。
さて、そろそろ次の新たな道も歩き始めようか。
Now's early dawn. Yeah, I'm starting to feel better. I crossed the pass yesterday. All that's left is a gentle downhill descent. However, there are steep roads in some places, and I have to make sure I don't fall. But don't get lost. There's still quite a bit of distance on this road, but I can already see where you want to get there.
Yes, I'm not walking through the tunnel anymore. The tunnel road that I had been walking until the day before yesterday suddenly turned into a mountain pass road yesterday, and now I'm in a situation that I have begun to descend on the way to the point of arrival. Let's walk quietly to the goal of "completion of the draft".
So, is it time to start walking the next new path?
↓
ところで、抽象性の高い細節(抽象的な言葉の多いパート)では、「キーワード」「キーフレーズ」「キーシーン」「柱(=地の文の基礎)と台詞(会話)」の順にディテール化を進めることになるな。たとえば「作品A」の場合は、第3章第1節2と第2章第2節2が、このアプローチで転がしていくことになるね。
………
うん、いい感じ。このモードにはいればOKだな。こにきてやっと、あの、昔の文士が原稿用紙にむかって頭を掻きながら、ときに苛ついて丸めた原稿をゴミ箱に放り投げるあのシーン。情況的には、あれと同じシチュエーションのライティング・モードにはいることになった。
つまり、これまでの制作行程を振り返ると、相対的に、草稿完成はそう遠くない、ということ。よし、ゴール目指してがんばるぞ!
↓
それにしても、「作品A」を書きながらつくづく思うのは、司直はなぜ、K協同病院のS医師を有罪にしながら、I市民病院のX医師を不起訴処分にしたのだろう。むしろ逆であるべきだった。
「事件」発生に10年の時間差があり、「発生」場所も異なることから管轄も変わってくるので、首尾一貫性を求めるのは“無理筋”かもしれないが、それでもはやり、知れば知るほど、調べれば調べるほど、この二つの事件に関しては「バランス」がとれていない。結論から言えば、X医師こそ「有罪」とすべきだった。
S医師の「主張」をつよく擁護するわけではないが、「看取りの医療/死をサポートする医療/死の側に立つ医師」としての「考え」は、医療の素人であっても、理解不能なものではない。
いっぽうX医師に見られる以下の5つの特徴のうち、1はS医師とは比較にならないほど「特異」なものであり、4の考慮も無視できないものがある。また、2と3も併せ考えたとき、殺人事件を構成しうる「未必の故意」が、7件の対象事案の随所にうかがわれる。にもかかわらず、司直はなぜ「不起訴」としたのか。
「X医師に見られる5つの特徴」(参考)
1:家父長的儀式性 2:脳死“状態”の恣意的判断 3:家族への病状説明から家族の依頼を引き出す 4:ベッドの逼迫事情の考慮 5:実行にあたっての家族の同意
自分としてはそこにも興味が湧くが、この作品ではそこまでは踏み込まず、S医師とX医師をモデルとした登場人物を設定し、前者を「是」、後者を「非」と位置づけ(この場合の「是/非」は「無罪/有罪」を意識したものではあるけれど直結したものではなく)、物語手法によって対比することにより、「尊厳死」と「安楽死」の関係性と、終末期医療の“望ましいあり方”について、私なりに迫ってゆきたいと思う。
…と、久しぶりに、肩をいからせて書いてみた。X医師の「所業」がそうさせたのだ。この人物(医師)には、基本的に”赦せない”ものを感じる。
これは「義憤」なのだろうか? いやちがう。その答えは、司直が「不起訴」にした“真意”にあると“感じ”ている。この“感じ”を作品のなかで表現する、すなわち“匂わす”ことができれば、書き手としては「成功」した(=がんばって書き上げた甲斐がある)と思っている。
で、その“真意”とは、S医師に関しては、時代背景も影響して「●●●●●●●」として検挙された。一方、10年後のX医師に関しては、上記「5つの特徴」にみるように、立件に必要な立証すべき事案の裾野が幅広いだけでなく、その多くが医療現場特有の生死に関するグレーゾーンの性質をもっていることから、X医師自ら自己弁護のために騒ぎ立てることにより、結果的に「一定の●●●●●を●●●●る」として、「不起訴処分≒無罪放免」にしたと推察される(なお、伏字は作品の根幹をなすキーワード群のため)。
さて、そういうことで、最後まで筆耕の手を休めずにやり遂げたい。
2022-10-06
きのうはずいぶん長くノマドしてしまったなあ。いつもの倍以上の時間。でも、はかどったな。これでやっと、ディテール・ベースのライティングにはいれる。そう、今日からね。がんばるぞ!
Yesterday I was a nomad for a long time. But it was back. NBut I did well. Now I can finally get into detail-based writing. So, starting today. I'll do my best!
↓
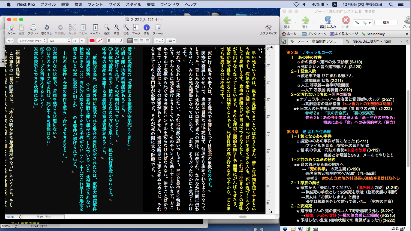
きょうは一日、部屋のなかで作業したけれど、きのうの長時間ノマドの成果がでてきた。iTextProのマーク設定を活用して、ワン・ファイルの中の全4章>各節>各細節単位で、全26細節をほぼパラレルで書き進めることになる。
その際、ディテールの弱い細節は、具体的な描写や会話に代えて、まずは、シナリオで言うところの「柱」あるいは、メインとなるシーン「キーシーン」の下書き、もしくは表現したい事柄についての「キーワード」「キーフレーズ」を書き込むことから始めることになる。
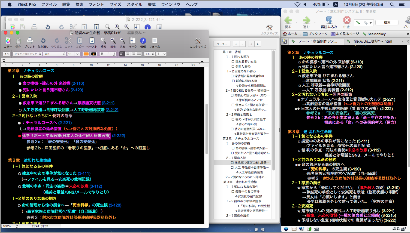
26個の細節のディテール化の程度はさまざまな現状。横一線にする必要はないけれど、ストーリー展開や伏線設定の関係もあるから、あまり凸凹だと進捗に支障がでるので、まずは「難所」から攻めてゆきたい。
最大の難所は、もともと強固な「岩盤」であった第3章第1節2のほかに、第2章第2節2も大きな存在感を持ってきたので、この二つの「山」をディテール化してストーリラインに取り込むことが、現時点でのいちばん大事な作業になっている。
でももう出口は見えている。慌てず焦らず一歩ずつ前に進むだけだな。
ちなみに、二つの画像のうち上の画像は、右サイドの章立て(目次、
SeaMonkeyベースのhtmlファイル) から開いた一細節の縦書画面(
iTextProベースのrtfファイル、草稿素案の段階)。下の画像は、章立て/目次画面と併置した本文加筆式目次ファイル(
iTextProベースのrtfファイル、マークリスト付き、縦横表示は適宜変更)。
2022-09-22
きのうは、ノマド先のマクドでよいシゴトができた。あのお店はよい仕事場になっている。ただ、平日にもかかわらず、午後7時あたりから、制服を着た近所の高校生とおぼしき若者たちの姿が目立ってきた。
彼ら/彼女らは、どうやら夜の早い時間帯、おそらく午後9時までだろうか、ここを勉強(自学)の場としているようだ。安いし広いし新しいし、雰囲気もいいし交通の便もいい。集まってくるのもうなずける。
そうなると、平日の昼下がりしか、ゆっくり寛ぐことはできないかもしれない。ただ、お目当ての、あの細長い“隠れ家”的なスペースは、いつも先客のいる 情況になっている。しかも、若い女性が一人で座っている姿をよく目にするようになった。なにかの資格試験に挑んでいるのかもしれない。
いずれにしても、平日のこのお店は、ノマドや自学する客が多いようだ。そのなかでも、自分はもっとも年上の準常連客ということになるのだろうな。
2022-09-18
先週土曜日から、ほぼ無音に近い情態に身を置いている。「作品A」の本格的なライティング(草稿執筆)に
はいれるようになった。やはりそうなんだ。ラジオ番組のトーク、いや、流れる歌声さえも、脳内想念のダイレクトなテキスト文字出力には、ブレーキになるようだ。ラジオから流れる言葉が、想念の言の葉に干渉するからだろう。
プロット構築時の“無から有を産みだす”作業では、いわば「ゾーン」(特定の事象へのやや過剰で持続的な集中情態)にはいるために、人的な交流まで含めて、もっと徹底して、そう、3か月ほどは、神経衰弱になるくらいぐっと、社会的活動が後退することになる。
その点、草稿作成は作業はそこまではいかないけれど、いよいよ本格的なライティング・モードにはいるとなると、音声ベースの言葉のシャワーからは遠ざかっていないと、仕事を進めることができない。
ラジオのよさの一つに、聴きながら“仕事”ができることにあるけれど、もちろん仕事もオーケーということではなく、自分の場合は、本格的な草稿執筆情態では、むしろ“無音”でないとはかどらない。BGMすらないほうがいい。
今回、やっとこの段階まできて、昔もそうだったことを思いだした。それを思いだしたことは大きい。この瞬間、「作品A」の最終的な出口が見えたから。
でも、ラジオを聴く時間も、これまでのようにもっていたい。とくにあの、最北端のコミュニティFMと希有な双頂山の麓にあるコミュニティFMの番組は。
そうなると、タイミングよく聴けない番組は、録音に頼ることになるな…。録音そのものはけっこうしてきたので、問題ない。ときおりトライしている「番組参加」のための投稿内容が、これまでよりも薄く短いものになるのかな…。
まあでも、ライティング・モードだけの日々も気詰まりだから、気分転換のためにも、セッメージ&リクエストの投稿は続けたい。ただ、忙しさにかまけて、こんどは真逆の、薄くて短くなりすぎると、それはそれで“不採用”が増えるかもしれない(笑;) そうなると、これまでほどではないにしても、メッセージ書きにもあるていど時間をさかないといけないかな…。
2022-09-17
不思議なもので、未明から「作品A」に取り組むことができた。「岩盤」は破砕したものの、その先の「ディテール」を目指したグラインドがなかなか進まないでいた。しかし、右サイドの章立てを兼ねたアウトラインを手直しして、それぞれの細節に対応したファイルのフォーマットを整形し直すことで、格段に書き進めやすい環境になった。
ちょっと目先を変えるだけで拓ける世界がここにもある。行き詰まるたびに投げ出したくなるけれど、ちょっと肩の力を抜いて向き合うと、意外に新たな取っ掛かりが見つかるのも、創作という世界の面白みとともいえる。「作品A」も、投げ出したい気分になっていたけれど、まだ続けられそうだ。投げずに、このまま仕上げまで進みたい。
だが、「作品A」ほど深入りしていない二部作「作品B」は、いまのうちに“断念”したほうがよさそうだ。若干形をなしている「作品B−1」は、三部作「作品C」の第三部「作品C−3」に、組み込む方向で活かすことを考えよう。「作品B−2」はまったくのイメージ段階にすぎないから、これは没にしよう。
ということで、ガチな「社会派小説」を書くのは自分には荷が重い、というか、力不足なことをひしひとと感じる。なので、それは「作品A」にとどめて、もうすこし「自由な発想」の物語世界を創ってみようと思う。
2022-09-16
この一か月間、酷暑なこともあって、なかなか集中しにくい情況が続いていた。ほかにも、気ぜわしいことが続いて、これもまた集中する機会を奪っていた。
でも、やっとそのことから、自分自身を“解放”することになった。よいことだと受け止めよう。そして、残暑が続くなかにも、比較的すごしやすい日々になってきた。そろそろ、本来のシゴト(=私事=Shigoto)モードにもどろうか。
2022-08-16
きのうは、おとといのマクドでのノマドに続いて、自宅で「作品A」に向かい合う一日だった。
もっぱら、複数のネタ本から、参考となる箇所をスキャナ使ったOCRでテキスト取得し、整形しする作業に追われてました。
きょうはこれから、そして、草稿が仕上がるまで、その整形データとネットからDLしたネタを、補強すべきパートに関係づけする作業を埋没することになります。
ところで、肝心の補強先にけっこう大きな変動が生じたので、まずはこの整理をしないといけません。けっきょくのところ、こんな感じになったかな。
(※)補強箇所の内訳(青文字は思弁性が高いので具体的描写には注意が必要)
第1章第1節2の2(延命に努めるR→昏睡から植物状態に)
第2章第2節2の1(日本人の死生観→終末医療〔看取りの医療〕)
第2章第2節2の2(ナチュラルコースへ〔主治医と看護師のカルテ〕)
第3章第1節1の2(司直の姿勢=未必の故意)
第3章第1節2 (命の保全から命の捌きへ→「死の科学」の死生観)
第3章第2節1 (尊厳死の手段としての安楽死→家族の頷き〔同意〕)
第3章第2節2の1(人工呼吸器取り外し=断命、未必の‘嗜好’)
第3章第2節2の2(予期しない急変→不手際)
第4章第1節1 (Rを起こすH)
第4章第1節2 (幻聴をへて覚醒へ)
うーん、第3章が大変だな。でも、すでにネタ化したイベントを各パートに“摺り込む”作業なので……言い換えれば、この作業自体は“無”から何かをひねり出す神経衰弱な作業ではないので、集中して取り組めば、比較的短期間で終わる……はず。
これから2〜3か月かな。これが終われば、草稿作成は終わったようなもの。年明けからは5〜7回ていどの推敲をへて、来年半ばには仕上がるかな……たぶん(^^)
そうそう、推敲を始めたら、同時に英訳も進めるので、いまの感触だと、完成はちょうど1年後くらいになるかもしれないね。英訳の完成はもう少し遅れるかな。
ちなみに、今回の構成ベースの「変動」は、いったん固まったはずの「構成=章立て」の改訂ということになるけれど、これは、「マクブックン」ではなく「マッケア」で取り組むようになってから、断然集中力が増した関係で、突如出てきたって感じです。
でも、「マッケア」は画面が小さく、文字も小さく、おまけにトラックパッドは扱いにくいのに、なんで?
たぶん、文芸創作関連と電子&紙出版関連のソフトとデータしか入れていないからかな。創作と出版は一直線でつながっているので、自分にとっては全体が一つの表現行為であり、「マッケア」はそのためのツールだからなんだろうなあ。
潔癖を期すために、ここでは翻訳作業すら排除しているのも、「(文字型)表現行為」に集中する上では、奏功していると思います。
それにしても「マッケア」、バッテリーの減りがはやいな。ま、AC電源アダプタもあるし、大容量ポータブルバッテリーも2個持ってるので、困ることはないけどね。ただ、持ち運び時にかさばるし、ちと重いのが玉に瑕(きず)かな^^;
さて、「作品A」の“先が見えてきた”、つまり、トンネルの出口が、まだ先ではあるけれど、はっきりと見えてきたので、二部作「作品B」のうち、「作品B−1」に着手するタイミングになってきました。
この作品、大まかなプロットはできているので、まずはパッド8で「章立て」までもってゆかなくては…。さ、きょうもがんばるぞ!
2022-08-12
さて……アタマがすこし軽くなってきたので、今日のこの日記も書いてみたい気分になりました^^;
「作品A」も手がつかない情態だったけれど、ディテール補強用のネタ探しができる情況にまでたどり着いたので、これから、補強箇所(※)に応じたネタを、手持ちの本からの抜粋や収集済みのネット情報を参照しながら、11パートそれぞれに割り付けてゆく作業が待っています。
今月末までには、この作業を終わらせたいな。それが済めば「作品A」の草稿はぐっと完成に近くなります。そこまでくれば、あとはディテールベースで、各パートの隙間を埋めるだけ。
さ、がんばるぞ!
(※)補強箇所の内訳(青文字は思弁性が高いので具体的描写には注意が必要)
第1章第1節2の2(昏睡から植物状態に)
第2章第2節1の2(司直の姿勢=未必の故意)、第2章第2節2の2(「死の科学」の死生観)
第3章第1節2の1(命の保全から命の捌きへ)、第3章第1節2の2(ナチュラルコースへ移行)
〃 第2節1の1(人工呼吸器の再装着) 、 〃 第2節1の2(尊厳死のための安楽死)
〃 第2節2の1(取り外し→秘匿の断命) 、 〃 第2節2の2(突発した不手際)
第4章第1節1 (Rを起こすH) 、第4章第1節2 (幻聴をへて覚醒へ)
2022-07-05
現在、草稿執筆中の「作品A]。視点(話者)は決まっていたけど、語られる「主人公」のキャラがいま一つ弱いままだった。そこで、メインとなる「事件」の主体を別な「人物」に変えることにし、その人物のキャラを「主人公」に組み込むことにした。これによって、従来の「主人公」のキャラの厚みを大幅に増すことができる。
ただそのぶん、「事件」を引き起こす「人物」のキャラは薄くなるけれど、それを埋めるために“強い信念”を付与することにした。結果、その「事件」の特徴がより明確に浮き出ることになるので、それはそれでいい感じになる。
なお、「事件」の参考にしているのは、東海大付属病院(1991年/神奈川県/有罪)、国保京北病院(1996年/京都府/有罪)、川崎協同病院(1998年/神奈川県/有罪)、北海道立羽幌病院(2004年/北海道羽幌町/不起訴)、射水(いみず)市民病院(2008年/富山県/不起訴)の、いずれも人工呼吸器に直接あるいは間接的に関係した、延命治療中止の事案。
2022-06-30
いよいよ「作品A」のライティング(筆耕)にはいります。これからは、言葉(まずは日本語)と真正面からの格闘になります(汗;)
目次にメモを書き込んだhtmlファイルをナビゲーターとして、iText Expressベースの縦書rtfファイル内で文字色をいくつか使い分けながら、全14個の「章>節>細節」に対応したrtfファイルをあちこち渡り歩いて、筆耕に筆耕をくり返してゆくことになります。
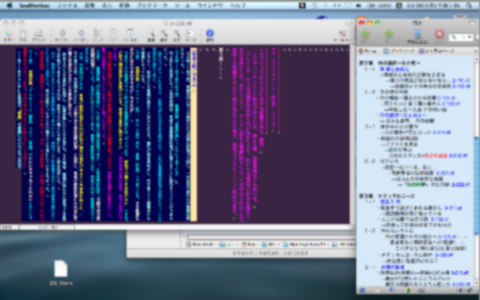
なお、htmlファイルとiText Expressベースのrtfファイルを統合して同時処理しているのが、SeaMonkeyになります。
ところで、「草稿作成」でもこの�最終段階になると、「ゾーン」にはいって神経衰弱になりそうになる……ということは、ないですね。イメージ(物語の世界観)の具象化がメインの作業と文字表現の彫琢作業とは、似ているようでじつは微妙に異なるので、使っている脳神経も別なようで、結果、少なくとも自分の場合は、すでに見えているトンネルの出口向かってどんどん近づいてゆくって感じですね。文芸創作の歓びがふつふつと湧いてくる作業になってきます(^^♪
なので、きのうウダウダと書いたように、次に出番を待ている作品たちに、ぐっと足を踏み込むこともできるようになります。……ということで、きょうもあしたも、コンスタントにがんばるぞ!
2022-06-29
「作品A」は、「草稿作成」という長いトンネルの中にあって、まだまだ先なので小さくはあるけれど、出口の白い光が見えてきました。この光が予定より1か月も早く見えたおかげで、「ゾーン」からも早めに抜け出ることができて、ほんとよかったです。
(パロディなどではない)独創性を前提とした文芸作品を創るにあたっては、自分の場合、創作の全行程のうち、「草稿作成」に着手して随所にディテールをふんだんに含んだストーリーラインが揺るぎなく固まるまでが、“精神的”にもっとも“苦しい”時期になります。
そんななか、この“難所”を独自ツールの「章話制作サブシステム」で思いのほかスムーズに切り抜けることができたのは、今回の「作品A」の創作にあたって大きな収穫でもありました。
この作品はまだ脱稿にないたっていませんが、いまや「出口」が見えていますので、日々粛々と「筆耕」をおこなうだけよく、時間の問題といえる情況になっています(とは言っても、完成する間までには、年内いっぱいはかかりそうですが^^;)。
さて、こうなると、このあと控えている「作品予定群」たちのうち、2番手の二部作「作品B(作品B1とB2)と3番手の三部作「作品C(作品C1〜C3)」を、上記サブシステムをそれぞれのプラットフォームとして、並行的に進めてゆこうと思います。
つまり、上記サブシステムをもとに、各作品の「草稿作成」作業における「筆耕」直前の「ブリッジ」創成を一応のゴールと定めて、このシステム内の具体的項目を埋めてしまうことにします。
具体的には、「ブリッジ」の前段の各作業、つまり、「構成(章立て)←→ストーリーライン(暫定)←→プロット練成(事件化)←→人物像化←→テーマ抽出←着想」を、遡行的あるいはサンドイッチ的なスタイルで相互干渉しつつそれぞれ充実させてゆく、という手法を採ることにしました。
これを上記5作品に対して、並行的に適用しながら制作してゆくことになります。これまで「並行3作(作品A、B,C」と呼んでいたものが、今後は「並行5作品(作品B1、B2。作品C1、C2,C3)になります。
そうなると「ゾーン」も同時に5個背負うことになる?
いえ、そうはならないですね。「ブリッジ」が草稿作成時の“流末”ではなく“プラットフォーム”になるので、これまでの“通常”の方法、つまり、川上から流れてきた玉石混淆のアイディアやシーンがここに“流末”ふうに集中する結果、物語の書き手としては、「ゾーン」と(勝手に名づけた^^;)極度にセンシティブな“精神情態”にはいらないと、満足できるレベルでの処理がうまくできない、などという悩ましいことは……ないですね。いわばサンドイッチふうに各作業が進むはずですし、結果、制作スピードもかなりアップするものと思われます。
では、「ゾーン」といういわば“魔術的”な作業がなくても、高品質な作品を創ることができるのか? できますね。ただし、この場合のポイントは、一連の制作プロセスの源流となる「着想」の次の「テーマ抽出」がしっかりできあがっていれば、ということになると思います。
かてて加えて、作品用にあつらえたサブシステム内の各項目を完成の域までもっていくために、その前段となる各作業内容を充実させてゆくという遡行的な手法を使うことになりますが、このことによって、5作にとどまらない複数作品の並行制作が可能になるだけでなく、それぞれの所要時間もかなり短縮されて、スムーズな制作が見込めるはずです。
でも、なんだかこうなると、文芸創作自体が、まるで、KDPで電子書籍や紙書籍(ペーパーバック)を出版するのと似たような、かなりシステマティックなもの(作業)になりますね。ちがいは、この手のルーチンワークとはちがって、文芸創作はやはり、表現内容の「独創性」が重要というか、勝負ということになりますね。
……うーん、ここまで、思い浮かぶままに書き連ねた今回のセミ・オートライティングは、かなり小理屈を並べ立てた、じつにくどい文章になりましたね(苦笑)
なぜそうなったか? じつは、ここまで書いてきた「考え方」そのものがまだ充分練れてなくて、その「考え」をまとめるために書いているからなんです。ま、これもまた「創作日記」の特徴と言っていいのかな……(微笑;)
2022-06-23
やっと、「作品A」の草稿後段「筆耕」への「ブリッジ(橋渡し)」の作業が終わりました。その間、「章話制作サブシステム:作品A用」を3回バージョンアップして、各章>節>場面のディテール枠を作成が完了しました。
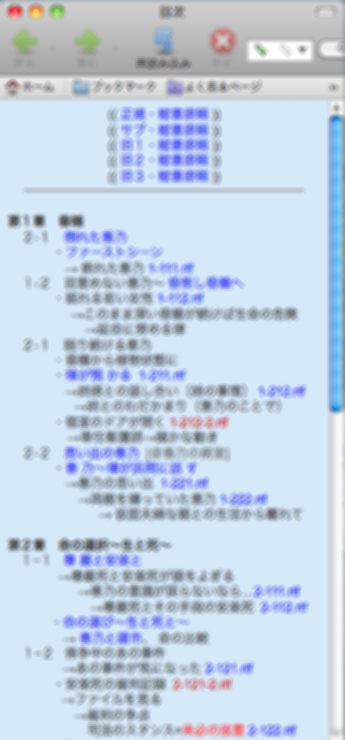
脚本で言えば、「箱書き」スタイルになるわけですが、自分の場合、物語りを作るときは、テーマや枠(構成)の“土台”を固めて^^;、“箱庭”方式で創作するのがいちばんしっくりきますね。急がば回れで、このほうが結局、仕上がるのもいちばん早いということが、今回あらためてわかったしだいです。
というわけで、「草稿作成」という長い長いトンネルの一人歩き……いまやっと、行く手の遠くに、出口の仄明かりが見えてきた、といった情況になりました。
きょうは6/23。当初の見込みよりすこし早いですが、お蔵入りしていた「章話制作サブシステム」をブリッジ・ツールとして使ったことが、思った以上に作業新着に役立った、という結果になりました。よかったです(^^)
でも、まだ「草稿」が完成したわけではなく、これからいよいよ、ディテールを書きこんでゆく「筆耕」作業に移っていくわけです。ワープロのない時代だと、原稿用紙に万年筆で書きこんでは、表現に行き詰まって原稿用紙を丸めて、つぎつぎとゴミ箱に投げ入れるあの“場面”に象徴される執筆作業ですね。
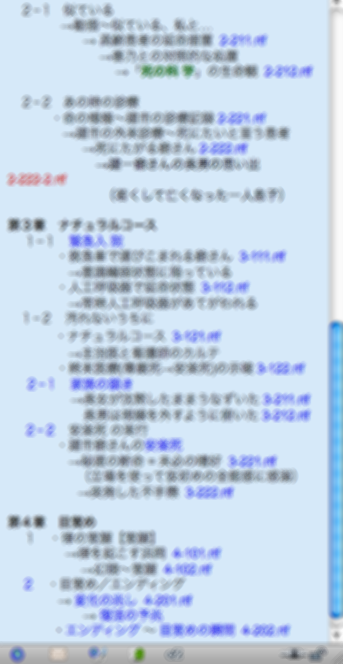
さて、そういうことで、ここでちょっと休憩(笑) 「草稿作成」作業の中でも、この「ブリッジ」にあたる部分が、自分にとっては、超センシティブでナーバスな作業パートになるので、ここを越えることができたと言うことは、これから少しずつ「社会復帰」できるということでもあります……今回も、壊れなくてよかった(笑;
これからの「筆耕」も楽ではないけれど、この作業は文章表現の粋を極めるといった基本姿勢になるので、“無から有を産む(というか、絞り出す)”ような、時に神経衰弱になったかのような、情緒不安定になるほどの葛藤と不安を内包した異様な作業とは趣が異なり、よくいう職人技の世界に近くなるぶん、文芸表現の巧みとして取り組んでゆく姿勢が基本の作業になります。
自分としては、ここまでくると、すり減らす「神経」がフェータルなものではなくなる(「ゾーン」から抜け出る)ので、ホッとひと安心です^^v
ちなみに今回は、「ゾーン滞在期間」がほぼ2か月になりました。前作のとき(長編SFミステリー『あの星座に』)がどれくらいだったか、10年ほど前のことなので覚えていないけれど、中編の「作品A」とちがって、400字詰め原稿用紙300枚以上の長編小説なこともあり、前回のほうがもっと長かったような気がします。いずれにしても2か月ですんでよかった^^;
さてと…、「草稿作成」が終われば、数次わたる推敲が待っていますが、この作業は草稿作成」時の(「構成」確定後の)ディテール・ベースな土台固め→ブリッジ(筆耕への橋渡し)→筆耕(いわゆるライティング)の一連の作業で味わう精神的な疲労に比べると、比較にならないほど“らくちん”ですね。
早くその段階まで行きたい。というか、早く脱稿したい(^^; ……うーん、書き終わるは、早くて年内かな^^; でもまあ、きょうをもって、あとは実質的に時間の問題になりました^^v
よし、ガンバル、まえにちょっとコーヒーブレイクだな(笑)
そうそう、二部作「作品B」の「B-1」はまだ「構成」確定にはほど遠い「プロット」練成の情態。「B-2」と三部作「作品C-1,2,3」はいずれも「構想」から「プロット」練成に踏み出したばかりの段階。なので、「ゾーン」の渦中で(神経衰弱すれすれの)情緒不安定になりながら、テーマと人物像を練りこんだ独創的な物語世界を追究する時期は、まだまだ先になります。
ということで、まずは、きちんと「社会復帰」しなくては^^b そしたら、ステロイドにも頼らなくていいかもしれないな……関係があるかどうかわからないけど、なんとなく、そう、なんとなくではあるけれど、ありそうな気がしなくなくもなきにしもあらなくもないかなって感じがなしよりのありかなあ……^^;
↑↓
いま振り返れば、
このエントリの6/4の記事はそれをうかがわせなくもないな……。でもま、もうだいじょうぶです^^b (次の作品の「草稿作成」までは……まだ、いつになるかわからないけど^^;)
(※)上携画像は、本文の「目次」ですが、創作メモを兼ねた未完成状態にあることと、作品そのものが出版予定であることから、内容はぼかしています。ごめんね^^; でも、おかげで着実に進んでますよ。ありがとう^^b


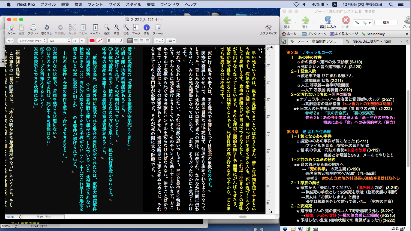 きょうは一日、部屋のなかで作業したけれど、きのうの長時間ノマドの成果がでてきた。iTextProのマーク設定を活用して、ワン・ファイルの中の全4章>各節>各細節単位で、全26細節をほぼパラレルで書き進めることになる。
きょうは一日、部屋のなかで作業したけれど、きのうの長時間ノマドの成果がでてきた。iTextProのマーク設定を活用して、ワン・ファイルの中の全4章>各節>各細節単位で、全26細節をほぼパラレルで書き進めることになる。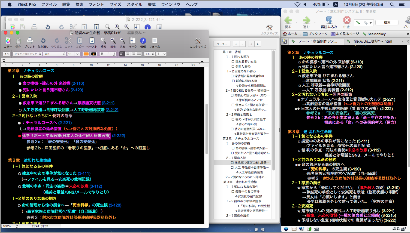 26個の細節のディテール化の程度はさまざまな現状。横一線にする必要はないけれど、ストーリー展開や伏線設定の関係もあるから、あまり凸凹だと進捗に支障がでるので、まずは「難所」から攻めてゆきたい。
26個の細節のディテール化の程度はさまざまな現状。横一線にする必要はないけれど、ストーリー展開や伏線設定の関係もあるから、あまり凸凹だと進捗に支障がでるので、まずは「難所」から攻めてゆきたい。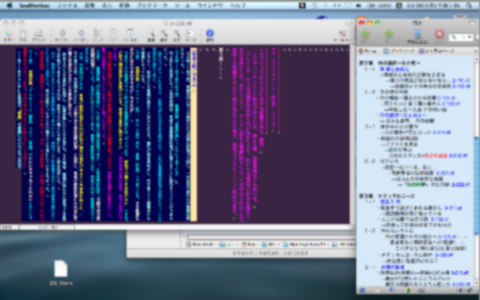
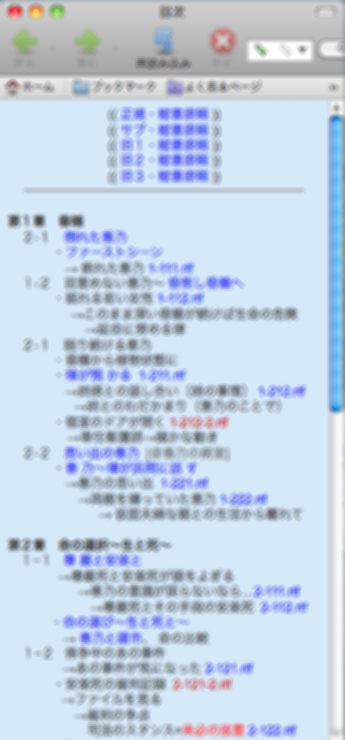 脚本で言えば、「箱書き」スタイルになるわけですが、自分の場合、物語りを作るときは、テーマや枠(構成)の“土台”を固めて^^;、“箱庭”方式で創作するのがいちばんしっくりきますね。急がば回れで、このほうが結局、仕上がるのもいちばん早いということが、今回あらためてわかったしだいです。
脚本で言えば、「箱書き」スタイルになるわけですが、自分の場合、物語りを作るときは、テーマや枠(構成)の“土台”を固めて^^;、“箱庭”方式で創作するのがいちばんしっくりきますね。急がば回れで、このほうが結局、仕上がるのもいちばん早いということが、今回あらためてわかったしだいです。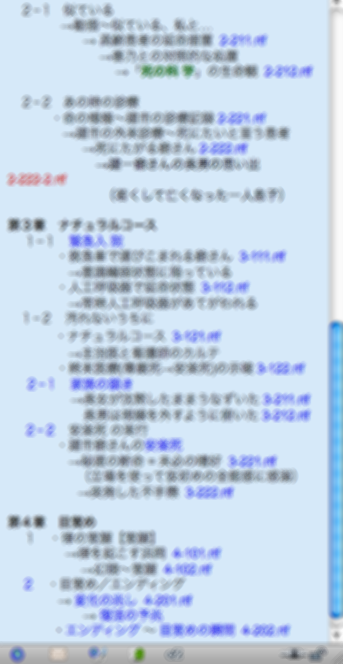 さて、そういうことで、ここでちょっと休憩(笑) 「草稿作成」作業の中でも、この「ブリッジ」にあたる部分が、自分にとっては、超センシティブでナーバスな作業パートになるので、ここを越えることができたと言うことは、これから少しずつ「社会復帰」できるということでもあります……今回も、壊れなくてよかった(笑;
さて、そういうことで、ここでちょっと休憩(笑) 「草稿作成」作業の中でも、この「ブリッジ」にあたる部分が、自分にとっては、超センシティブでナーバスな作業パートになるので、ここを越えることができたと言うことは、これから少しずつ「社会復帰」できるということでもあります……今回も、壊れなくてよかった(笑;